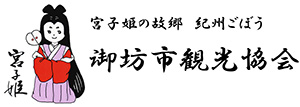宮子姫の故郷 紀州ごぼう 御坊市の観光情報が満載!遊んで!食べて!泊まって!御坊を満喫しよう。

イベントカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| □ | … 営業日 |
| ■ | … 休日 |
| ■ | … イベント |
熊野古道
熊野古道について
| 熊野古道とは熊野三山へつづく参詣道の総称のことで、大きく分けて紀伊路、小辺路、中辺路、大辺路、伊勢路があります。御坊市を通る熊野古道は紀伊路に分類されており、当時は京都や大阪から来る巡礼者の宿場として大変栄えたと伝えられています。 御坊市は比較的平坦な道が多い区間ですが、かつては大河川日高川を渡らなければならないということで命がけの難所でありました。それら苦難の道を超えることにより魂が浄化され、熊野三山に参ることで生きながら「生まれ変わる」と言われています。 現在は王子神社と5社の王子社跡、道沿いには歴史ある寺社や遺跡が残っておりますので、かつての時代を想像しつつ、散策を楽しまれてはいかがでしょうか。  |
① 善童子王子跡
 |
善童子王子跡 御坊市湯川町富安 善童子王子は、「連同持」「田藤次」「善道子」「出王子」「出童子」「富安王子」などの別名があり、王子社の中でも最もたくさんあります。 明治時代に湯川神社(御坊市湯川町小松原)に合祀されました。仁和寺蔵の『熊野縁起』(嘉暦元年(1326))には、准五体王子の一つにあげられているなど、王子社の中でも歴史が古く重要な位置を占めていました。 |
② 愛徳山王子跡
 |
愛徳山王子跡 御坊市藤田町吉田 『後鳥羽院熊野御幸記(明月記)』(建仁元年(1201)10月10日)において、連同持(善童子)王子の次に「・・次又愛徳山・・」とこの王子社の名が初めて記されており、鎌倉時代初期には所在していたことがわかります。 また、『明月記』(元久2年(1205)正月1日)に「・・盛範愛徳山王子修造功・・」と熊野別当家の一族盛範が愛徳山王子を修造した功によって賞せられた記事があり、仁和寺蔵の『熊野縁起』(嘉暦元年(1326))には、准五体王子に位置付けられるなど鎌倉時代を通してかなり重要な王子でありました。周辺の竹藪が熊野古道独特の情緒があります。 |
③ 海士王子跡
 |
海士王子跡 御坊市藤田町吉田 「海士王子」周辺は、道成寺創建にかかわった文武天皇夫人宮子の生誕の地(九海士の里)との伝承があり、「海士王子」に祀られていた御神体の木像は、明治時代に八幡神社に合祀されたときに、道成寺に移され「宮子姫」の像として祀られています。 |
④ 岩内王子跡
 |
岩内王子跡 御坊市岩内 『紀伊続風土記』に「也久志波王子社、境内周三十四間、村中にあり岩内王子を祀るという。岩内王子は『御幸記』に出たり。此地河流変遷し、岩内王子の社没して、後に小社を此に建しという。」とあります。王子跡の滅没は、元和元年の大洪水で名屋浦が全滅した時と言われています。 |
⑤ 塩屋王子神社
 |
塩屋王子神社 御坊市塩屋町北塩屋 社は古く、著名な王子社であったようで、天仁二年(1109)藤原宗心郷の『中右記』に「塩屋王子に至り奉幣す」とみえます。境内に御鳥羽上皇在所の跡と伝える御所の芝跡が、石段の登り口の右に仁井田好古の王子祠碑があります。別称美人王子といわれています。 |
⑥ 仏井戸
 |
仏井戸 御坊市名田町上野 『紀伊続風土記』に「上野王子の旧地。井戸の仏三体あり古の王子の本地仏にして、…略…」とあり、上野王子社の旧社地であります。仏井戸には地蔵菩薩・阿弥陀如来・観音菩薩の仏像が刻まれています。年に2回、井戸の水を汲み出して清めます。井戸は晴雨に関係なく水深が変わらないといわれています。本来の名前は「井戸仏」です。 |
⑦ 上野王子跡
 |
上野王子跡 御坊市名田町上野 上野王子については、『後鳥羽院熊野御幸記』(建仁元年(1201)10月10日)において、「・・次うえ野王子野径也・・」と上野王子のことが明記されています。また、上野の地は中世宿所として相当重きをなしていました。 王子の位置については、参詣道の移動した江戸時代初め頃に現在地に移ったと考えられています。 |